「教育を通じて世界を知る」― 佐藤廉太朗さんが語る東ティモール教育ボランティア体験
海外プログラムに興味はあるけれど、どんな経験が得られるのか想像がつかなくて踏み出せない。
そんな不安を抱える方も多いのではないでしょうか。
今回は、日本財団ボランティアセンターが主催する「東ティモールでの教育ボランティア」に参加した、国際教養大学1年生の佐藤廉太朗さんにお話を伺いました。高校時代からさまざまな国を訪れ、教育や移民分野に強い関心を持つ佐藤さん。東ティモール滞在中の活動内容や現地の様子、さらにそこで得た学びについてたっぷりお伝えします。
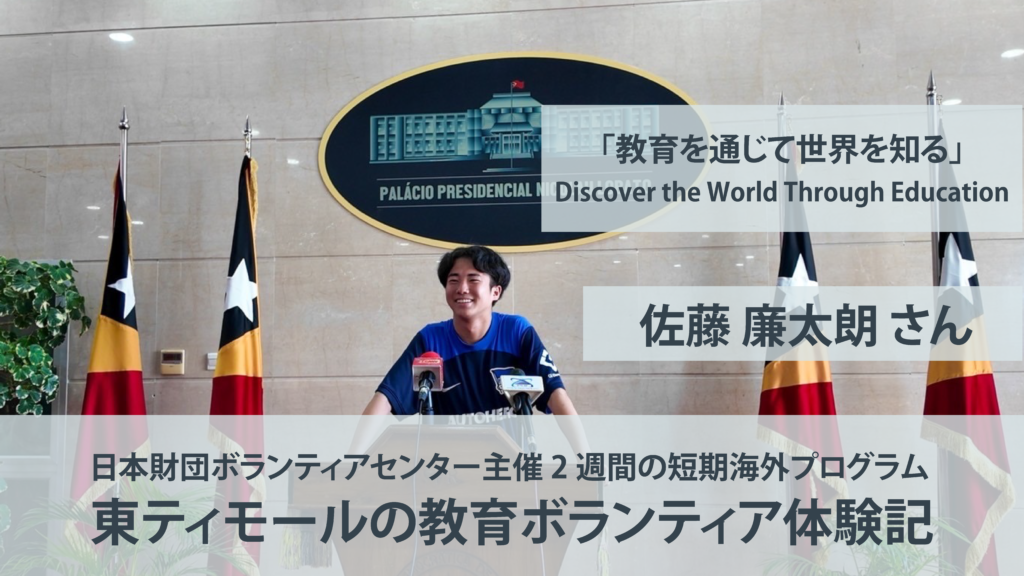
そもそも東ティモールってどんな国?
東ティモール(正式名称:東ティモール民主共和国)は、東南アジアで最も新しい独立国家の一つです。2002年にインドネシアから独立し、首都はディリ。公用語はテトゥン語とポルトガル語で、宗教はカトリックが大多数を占めます。
石油などの天然資源を有する一方で、農業や教育、医療などのインフラがまだ整いきっておらず、国際協力や教育ボランティアの現場として注目されています。また、海洋生物の多様性が世界的に高く、ダイビングスポットとしてのポテンシャルも秘めている国です。
「東ティモール」という名前を耳にする機会はまだ少ないかもしれませんが、その分だけ現地の人々の暮らしや社会、文化に間近で触れられるのが魅力です。国際支援の最前線を自分の目で見ることができるため、海外ボランティアやグローバル教育に関心がある方には絶好のフィールドです。
高校時代の経験から「教育×移民」に興味を
Q. まずは自己紹介をお願いします。
国際教養大学(AIU)1年生の佐藤廉太朗です。
AIUは秋田にある公立大学で、すべての授業が英語で行われます。同じ志を持った仲間たちが集まる環境で、刺激的な日々を過ごしています。
もともと国際基督教大学高校(ICU高校)出身なのですが、ICU高校は全校生徒の8割近くが帰国子女など国際経験豊かな学生で、それまで海外経験が一切なかった私は、国内にも関わらずカルチャーショックを受けました。そうした同級生たちの話を聞いているうちに、外国の文化や国際問題に興味を持つようになりました。
AIUでは2年生から学部内での領域を選択します。私は、国際関係学などを学ぶグローバル・スタディズ(GS)という領域への進学を考えています。学生全員が、一年間の海外留学を義務付けられており、EducationやMigrationを専攻できる大学に行けるよう頑張っています。また、学生はほぼ全員が学内の寮で生活するのですが、最初のルームメイトが20代後半のパキスタン系ドイツ人で、文化も年齢も異なる人との生活は刺激的でした。
ICU高校、多様で面白そうな人たちが集まってそうですね。前回、ケンブリッジでの経験についてインタビューを受けてくださった飯田さんもICU高校出身でした。そしてAIUも国際色豊かで、秋田での共同生活を通じて、たくさんの仲間ができそうですね。
高校で多様なバックグラウンドを持つ人たちと交流するうちに、国際社会と、その中に位置する日本の問題について関心をもつようになりました。高校3年生のときには「トビタテ!留学JAPAN」を利用してドイツとデンマークへ渡航し、移民や教育に関するリサーチを行いました。
もともと学校の先生になりたいと考えており、教育に興味を持っていました。ただ、日本の学校教育の現場では、海外にルーツをもつ子どもたちが生活・学習面で困難を抱えていることを知りました。また、年齢に関わらず、移住・避難先で問題なく生活を送るために必要な知識を身につける機会が、移民・難民には保障されていないと感じました。
そこで、本人の意思に関わらず海外に移住した人々の悩みや課題を解決する必要性を実感したのです。そういった観点で、教育方面から移民問題にアプローチできる「教育×移民」というテーマに関心が深まったという経緯がありました。
「教育×移民」、これからの日本においても最重要テーマですね。ドイツやデンマークでは、具体的にどのような活動をしてきたのでしょうか?
ドイツは、ちょうどロシアのウクライナ侵攻が始まった時期で、当時は国内のウクライナ難民が急増していました。そこで、移民・難民関連のボランティア団体や行政機関、語学学校、民間のNPO/NGOを訪問して、支援現場の取り組みや現状を学んできました。
ドイツで実施している移民・難民の支援を日本国内でどのように適用できるか、という観点でヒアリング・ディスカッションをしたり、実際に運営の手伝いもしていましたし、街角インタビューを実施したりもしてきました。
デンマーク・オクスボル(Oksbøl)には、UNHCRが監修する世界唯一の難民ミュージアム「FLUGT」があり、そこでの展示から学びを得たり、職員の方に話を伺ったりしました。また、デンマークは教育先進国ということもあり、コペンハーゲンで学校の先生にインタビューしたりもしました。
高校生で、目的・課題意識を持って実際に海外を訪れてリサーチをする行動力、すごいですね。ヨーロッパでは、移民・難民問題は常に大きな争点ですよね。
また、トビタテはこうした留学ではない海外でのリサーチ・フィールドワークもサポートしてくれるのは大きな魅力ですよね。私も大学生の頃、トビタテのサポートで留学経験があります。トビタテでできる繋がりも大きな魅力です。

教育ボランティアで東ティモールへ
Q. 今回参加された東ティモールの教育ボランティアは、どのようなプログラムなのでしょうか?
日本財団ボランティアセンターが主催する、2週間ほどの短期海外ボランティアプログラムです。首都ディリを拠点に、子どもたちの教育支援を行うのがメイン。学校や国際機関、民間支援団体を訪れて、東ティモールの教育現場を学んだり、一緒にアクティビティをしたりしました。大統領府の敷地内にあるフリースクールを訪問できたのは特に印象的でしたね。
日本財団ボランティアセンターのプログラムなんですね。私も参加経験があります。個人の旅行では味わえないような経験ができるところが魅力ですよね。
経済面でのサポートも大きく、東ティモールへの渡航費や宿泊費、参加費などすべて含めて3万円でした。私の学校は授業への出席なども厳しく、長期的に休みを取ることは難しいので、2週間という期間もちょうどよかったです。
海外渡航は、航空券やホテル代だけでも大きな負担です。さらに円安も加わり、どんどん海外へ行くハードルが高まってしまっていますよね。きっかけポータルでは、そうした課題を解決するため、大きな経済的負担なく国内外のプログラムに参加できたり、返済不要の奨学金が得られるような機会を紹介しています。
Q. 東ティモールで訪れたフリースクールとはどのようなところなのでしょうか?
東ティモールの大統領官邸には、国民であれば誰でも教育を受けられるように無料の学校が建てられています。若者の教育を重視する大統領の意向に沿って設立されたその学校では、午前・午後でそれぞれ60-120名ほどの子どもが授業に参加し、テトゥン語、ポルトガル語、インドネシア語といった言語の他、数学、音楽、体育、美術などを学んでいました。子どもたちが大統領と遊ぶ姿も見かけましたし、私たちも大統領や補佐官の方と交流させてもらいました。
政府と市民や子どもたちとの距離がこれほどまで近いことは非常に驚きでした。官邸内の政府関係者や軍人、子どもたちや保護者、市民の人々と話した際に、全員が友達のように優しく接してくださったことも印象的です。
大統領の距離がそこまで近いしいのは驚きですね。セキュリティ的にも先進国では見られない風景です。
Q. ディリの中心地や現地の学校を訪問してみて、どんな印象を受けましたか?
首都のディリでさえインフラが十分とは言えず、スラムのような場所もありました。収入は少なく、生活・衛生用品なども不足しており、町の人も、なかなか困っていることが多いと話していました。ただ、そのような環境の中でも、現地の人はとても温かく私たちを迎え入れ、笑顔を絶やさずに接してくれたことは、とてもうれしかったです。
フリースクールは、東ティモールの中では比較的良い施設なのですが、プールの水があまり綺麗ではなかったり、教科書や筆記用具が不足していたり……改善すべき点はたくさんあると感じました。教科書もボロボロのものを皆で共有しながら使っているのが現状です。今回のプログラムでは、日本財団と参加者のそれぞれが、文房具などの物資支援も行いました。
現地に行ったからこそわかる課題や気づきですね。暖かい笑顔を向けてもらっている姿が想像できます。
Q. 他に訪れた学校や機関についても教えてください。
ディリ郊外の学校や、山のほうにある学校にも行きました。なかには、日本や中国からの支援で作られた校舎もありましたね。東ティモールは若い国で、子どもたちの数も多いので、先生の数が足りていないところも多いようです。また、感染症予防や保健衛生の普及のために、移動式の病院が定期的に訪れるなど、国際協力の最前線を目の当たりにしました。
個人の旅行では、学校訪問やそこでの先生・子どもたちとの交流はなかなか難しいですよね。こうしたプログラムだからこそ味わえる、貴重な経験ですね。

Q. 実際に学校でどのようなアクティビティをしたのでしょうか?
3つの学校を訪れましたが、各学校でのメインアクティビティとして実際に子どもたちに対し授業を実施してきました。また、先生方に各学校の実情や課題をヒアリングしたり、先生のアクティビティのサポートをしたりもしてきました。
学校のプールで子供たちと一緒に泳いで遊んだり、自由時間に現地の人とサッカーをしたりといった交流もできました。また、街中の人にインタビューを実施し、家に招いてもらって生活の様子を聞いたりと、プログラム以外でも貴重な経験ができました。
どのアクティビティも魅力的ですね。特に、街中の人にインタビューを実施して現地の暮らしを知るなんてとても面白そうですね。その発想や行動力もすごいです。
Q. 現地の方へのヒアリングは英語で実施したのですか?
家に招いてくれた方は、オーストラリアで働いた経験があったため英語でした。ただ、やはり英語が通じないことがほとんどなのでGoogle翻訳を利用したりもしましたし、渡航前に公用語であるテトゥン語を学んだので、テトゥン語でのやり取りもありました。
事前にテトゥン語を学んでいったのですね!現地の方もテトゥン語で話しかけてもらえると嬉しかったでしょうね。日本でも教材がほとんどなさそうなイメージですが、そうした言語をしっかり事前に学び、実際に活用してくるなんて素晴らしいの一言に尽きますね。

参加のきっかけと選考の流れ
Q. このプロジェクトに挑戦しようと思ったきっかけは?
高校2年生のときにカンボジアで教育系のボランティアをしたのですが、その体験を経て途上国の教育現場にもっと関わりたいと思うようになったんです。ちょうど大学の授業のスケジュールの合間を縫える2週間程度のプログラムを探していたら、東ティモール行きの募集を見つけました。経済的支援があったのも大きかったですね。
途上国の教育系プログラムといった観点ではピッタリのプログラムですね。学生にとって、経済的な支援は大きいですよね。せっかく自分の興味にピッタリ合致したプログラムがあったとしても、金銭面で諦めてしまうことって多々あると思います。
Q. 選考のプロセスはどのように進んだのでしょうか?
2回で合計人数20人の募集に対して、応募がのべ340名ほどあったそうです。最初は志望動機を400字程度で書き、次に面談という流れでした。私はカンボジアやドイツ・デンマークでの活動について話しつつ、ポルトガル語由来のテトゥン語を少し勉強していった成果もアピールしました。「教育に対してどんなアイデアを持っているか?」など具体的な内容を伝えられたのが良かったかもしれません。
自分の過去の体験と紐づいた想いがプログラムの趣旨と合致していて、強いアピールポイントになっていそうですね。さらに応募の段階からテトゥン語の勉強をしていたのは本当にすごいです。強い想いが伝わりますね。私が選考担当でも、絶対採用していると思います。
東ティモールで得た学びと気づき
Q. 佐藤さんにとって、今回の海外プログラムで最も印象に残っていることは何ですか?
なんといっても、人々の温かさですね。東ティモールの方々は、助け合いや共助の意識が強いように感じました。外国人の自分たちが挨拶しても、満面の笑みで返してくれて、短い期間の中でも本当に多くの人々と友達になりました。家に招いて話を聞かせてくれた男性も、もし隣人が食べ物に困っていたら、たとえ自分たちが貧しくても一緒にご飯を食べるだろうと語ってくれました。また、物資が不足している一方で、天然資源(石油)が国の財源になっている点や、医療費が無料であることなど、「困っている人を放置しない」という社会のあり方には驚きました。
日本に帰ってきたときは、日本人と東ティモール人の接し方や親しさの差を感じ、少し寂しくなりました(笑)。食事もどれもおいしいものばかりだったので、もし海外に移住するなら東ティモール一択ですね!
南の島国ならではの暖かさ、人懐っこさってありますよね。そして、このプログラムを通じて、将来の永住先候補まで見つかってしまったのですね!笑
Q. 教育面や国際協力について、どのような気づきがありましたか?
インフラ面の課題はもちろんですが、子どもたちに対する熱意や、国際機関・NGOの支援がしっかり届いている部分も多いと感じました。まだ独立して日が浅い国ですが、若い世代が多く、明るい未来を信じて頑張っている姿が印象的でした。私自身、「教育と移民」というテーマにもっと深く関わりたいと思ったし、この経験は必ず将来の活動の糧になると確信しています。
インターネットでいくら調べても、実体験に勝るこうした気づきは得られません。佐藤さんの将来の活動に向けた、重要な経験になったことは間違いないと思います。
東ティモールは日本人にとってまだあまり有名ではない国ですが、だからこそ学べることが多いです。こうした取り組みを通じて、日本との繋がりが大きくなると嬉しいですね。
もし現地に行く機会があれば、渡航前に現地語を覚えておくとさらに深く交流できるのでオススメです。
日本人は、東ティモールという名前すら知らない人がほとんどかもしれませんね。そうした国に繋がりができたというだけで、日本との関係を深める一歩に既に大きく貢献できていると思います。

最後に、これから挑戦したい方へメッセージ
Q. これから海外プログラムに挑戦したい人へ、一言メッセージをお願いします。
私自身、高校生の頃から「国際機関に入りたい」「移民や難民支援をしたい」という漠然とした夢がありました。でも、どうやって関わるのか、どんな勉強をすればいいのか分からなかったんです。ただ、実際に現地に足を運んで自分の目で見て、体験してみることで、一気に視野が広がりました。
私自身もそうでしたが、日本の学校に通っていると、「どうしても学ぶ=机に向かう」になってしまいがちです。しかし、全くもってそんなことはありません。私にとって留学や現地調査の価値は、「人や環境と対話を交わすこと」だと思います。「ひとりひとりが不安に感じていることは何か」「なにを私たちに求めているか」という情報は、論文などに掲載していることも少なく、現地の人との対話からしか知ることができません。人道支援において最も尊重されるべきである、人々の暮らしや感情を、生で聞くことができるのは、現地へ赴いた人の特権です。また、「なぜこの場所で問題が起こっているのか」「他の場所ではできることがなぜここではできないのか」といった疑問は、現地に赴き、その環境の中で思考し、実践・リフレクションを行う…というプロセスを経ることで、より本質的な気付きを得ることが出来ると考えます。
難しく考えなくとも、現地に足を運んで体験してみるだけで学べることがたくさんあります。知識は後からいくらでもついてきます。興味があればまずは応募してみること。失敗を恐れず動き出すことが、夢への第一歩になると思います!
興味を引く機会があれば、まずは応募して挑戦みること。そして楽しんて学ぶこと。本当に大切ですよね。
体験しないと学べないことで世の中は溢れています。ただ、漠然と怖い気がしてその一歩を踏み出せないままでいるのはもったいない。
佐藤さんの体験談を通じ、一歩を踏み出すことの大切さ、現地での体験の面白さを学べたのではないでしょうか。
きっかけポータルでは、金銭的な負荷なくこうした面白い体験ができるプログラムや給付型奨学金などを紹介しています。興味あるものから、どんどん応募してみましょう↓
経験が生む新たな視点
東ティモールの教育ボランティアに参加した佐藤さんの体験談を通じて、「教育支援」と「温かい地域コミュニティ」という、まだ知られざる東ティモールの魅力が見えてきました。日本とは異なる社会や文化に飛び込むことで、学ぶことは無限にあります。
「海外プログラムはハードルが高い」と感じている方も、まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。日本財団ボランティアセンターをはじめ、多くの団体が学生向けの支援制度や短期プログラムを用意しています。一歩を踏み出せば、想像以上に視野が広がるかもしれません。
あなたも佐藤さんのように、「わからないからこそ、自分の目で確かめたい」という思いを大切に、未知の世界へ飛び込んでみませんか?いつか、今回の体験談があなたの次の挑戦の“きっかけ”になれば幸いです。





